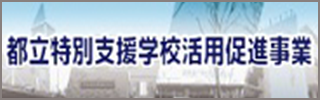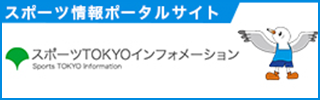疾走する喜びと感動
日常の行動範囲を広げてくれる
スポーツ用義足に初挑戦!
〜東京都パラスポーツ次世代選手発掘プログラム
スポーツ用義足事前体験会〜
カーボンの板バネで颯爽と走る、スポーツ用義足の選手を見たことがあるでしょうか。未経験者にとってそんな軽やかな疾走や歩行は、踏み出すのにも勇気がいる世界かもしれません。
現在東京都と公益社団法人東京都障害者スポーツ協会では、鉄道弘済会義肢装具サポートセンター協力のもと、その一歩を後押ししてくれる「スポーツ用義足事前体験会」を開催しています。
これは同共催による「東京都パラスポーツ次世代選手発掘プログラム」の前段を担う催しとして2024年から新しく始まった体験会です。今回は2024年11月9日、東京都立北特別支援学校体育館にて行われた義足体験会を取材、参加者の声をお伝えします。
競技スポーツへの扉を開く「義足体験会」
熟練の手で調整から練習までをサポート
カーボン製の板バネ(カーボンブレード)を利用したスポーツ用の義足(以下スポーツ用義足)は、板バネのたわみの反発を利用して走る、疾走に特化した義足です。スポーツ用義足は、板バネのみならず、脚の断端部(※1)と義足をつなぐソケット、場合によっては膝関節機能の代わりをする膝継手(つぎて)、それらをつなぐ各種コネクター等さまざまな部品を、利用者の特性や状況に応じて組み合わせていく必要があります。そのため、利用者ごとに必要となる部品が異なり、加えて義肢装具士(※2)による細かな調整が必須となりますが、それによって、利用者に義足がフィットすることで、より軽快な動作が可能になります。日本では1980年代後半に鉄道弘済会義肢装具サポートセンター(以下義肢装具サポートセンター)(※3)が初めて導入、義足の可能性を広げてきました。
(※1)切断後の残された脚の部分のこと
(※2)病気や事故などで身体の一部や機能を失った人のために、人工の手足(義肢)や装具を製作する専門家
(※3)義肢や装具の製作から装着訓練までを担う民間で唯一のリハビリテーション施設。スポーツ用義肢を扱い、義手・義足のアスリートを支えている
今回の「義足体験会」では、参加者の状況に合わせて、体験会側がスポーツ用義足の部品をあらかじめ用意、会場で義肢装具サポートセンターの義肢装具士が調整します。参加者は義足を装着した後に、同センターの理学療法士や著名な義足アスリートから、義足の使い方や基本動作を学ぶことができます。

「まず体感して頂くこと、可能であれば競技大会に出場し、国際大会に羽ばたいていって頂けたらという趣旨ではありますが、なにより一生涯のスポーツに出会い、続けてもらいたいというのが大きなポイントです。走れるようになることで少しでも自信がつけば、外に出てみよう、運動してみよう、いろんな人とどこかへ行ってみよう、そんなステップに繋がるのではと思っています」(東京都障害者スポーツ協会スポーツ振興部部長・藤田勝敏(ふじた かつとし)さん)
今回義足体験会に参加するひとり、足立区在住の執行孝幸(しぎょう たかゆき)さんは、先天性疾患の発症により右大腿(太もも部分)切断、日常用の義足を作りました。少し不安もありつつ同じ境遇のコミュニティを求め、また、運動ができるようになることで日常の健康維持にもなると考え、参加を決めました。
「2022年の11月に切断し、2023年7月に義足を使い始めて2023年10月に退院しました。日常用の義足にもまだ慣れてはいないのですが、よろしくお願いいたします」(執行さん)

義肢装具サポートセンターからは、義肢装具士(以下PO)の村上智貴(むらかみ としき)さん、理学療法士(以下PT)の山本一樹(やまもと かずき)さんが運動指導に当たります。続いて講師としてパラリンピアン(陸上・100m/走り幅跳び)の大西瞳(おおにし ひとみ)さん(※4)が紹介されました。

(※4)大西瞳(おおにし ひとみ)さん
1976年東京生まれ。2000年、風邪から心筋炎を発症、右足大腿を切断。中学高校と陸上部だったことから義足での陸上競技を始め、100m、走り幅跳びで片足大腿義足クラスのトップアスリートに。リオ2016パラリンピック日本代表、世界陸上3大会連続出場などで活躍。スタートラインTokyo所属。
少しの勇気と継続した練習の末に
その世界が広がっている
開会式での簡単な自己紹介の後、早速体験開始です。まずは日常用義足のまま準備運動、次に事前にPOが参加者向けに調整したスポーツ用義足を装着します。ソケット部のフィット感、継手やブレードなどを調整し、次はいよいよ基本動作の練習です。PTや講師に支えてもらいながら、片足でのバランス調整、重心をかける、歩く、止まる、横歩きなど順を追って練習すると、参加者はよろめきそうになりつつも、徐々にブレードに乗る感覚を掴んでいきました。日常用義足と比べ接地面や重心が前方にあり、グッと踏み込むのには勇気がいりそうですが、ここで重要なのは義足と体が合っているかどうかです。歩く、跳ぶといった動作を繰り返しながら、PO村上さんが必要に応じてパーツ交換やボルト調整を行い、参加者にしっかりと合う義足に仕上げます。PT山本さんと大西さんが、伴走しながらアドバイスや声掛けをし、コツを掴んだ執行さんの表情が一気に明るくなる瞬間が印象的でした。



体育館での基本動作の後は、隣にある東京都障害者総合スポーツセンターの屋外の運動場に移動し、歩行・走行体験へと進みます。競技場では、義足ランナーチーム「スタートラインTokyo」の練習会も行われており、義足の走者たちが和気あいあいとコミュニケーションをとりながら、思い思いに疾走していました。このクラブのランナー兼選手会長水谷憲勝(みずたに のりかつ)さんはその位置付けをこう語ります。

「義肢を作り社会復帰をした後、病院では教わることができないことをメンバー間で補って、歩き方から次のステップまでをお手伝いするようなクラブチームです。日常用義足で歩く人もいれば、ブレードで全速力で走る人もいます。半年くらい続けると笑顔になってきて、その人はまた新しい人に教えて、という循環が続いています。」(水谷さん)
切断の原因も状態も異なる方々が全国から集っているとのことで、今日は50名ほどが参加、メンバーは200名以上もいるのだそうです。その中心には、チームの創設者で、スポーツ用義足の日本初導入に尽力した義肢装具サポートセンター臼井二美男(うすい ふみお)さん(※5)の姿がありました。

「定期的にやらないと走る動作を維持できないので、どこかで月一回くらいと思って始めて35年経ちました。中にはパラリンピアンになった人、競技を引退した人もいて、彼らも参加していますよ。皆でいろんな競技をしに行きますが、やはり走りが基本。走れる人は上手に歩けるし、いろんなスポーツにいけるので、まずランニングからと思って続けています。最初は不安だし、自分の体に自信がないと思いますが、回数を重ねていくと、だんだん競技力も上がるしハートが強くなる。チャレンジ精神みたいなものが生まれてきますから、ぜひ運動を継続してほしいです。ここにくれば仲間がいると思えますから」(臼井さん)
(※5)臼井二美男さん
鉄道弘済会義肢装具サポートセンター勤務、切断障害者へのスポーツ用義足指導など幅広い活動を行っている国内義肢装具士のレジェンド。1989年通常の義足に加え、スポーツ用義足の制作も開始。2020年現代の名工、第9回ものづくり日本大賞内閣総理大臣賞、2023年黄綬褒章受賞。1955年群馬県出身。
トラック中央では執行さんが、大西さんや山本さんとの練習で走りをぐんぐん上達させ、1時間後には軽やかに走る姿が見られました。トラックには楽しげなランナーたちの声が響き渡っています。

「走ることがこんなにも
特別なことだと気付いた」(執行さん)
「日常にも自信がついて、仲間ができる。
それを皆にも知ってもらいたくて」(大西さん)
初めて体験するスポーツ用義足に戸惑いつつも、終盤には感動の疾走を経験するまでになった執行さん、練習時間いっぱいを使い、歩行と走行の練習を続けました。
「最初は日常生活の義足と感覚が全然違って難しかったですけれど、慣れたら走れるようになって、良かったです。義足になって以来、走れると思ってもみなかったですし、ここまで走れるとは思いませんでした。ふわんふわんと雲の上を飛ぶような不思議な感じ。走ることがこんなにも特別なことだったと、義足になって気がつきました」(執行さん)
今日一日サポートした大西さんは大きく頷き、執行さんの挑戦を讃えます。普段からイベントに積極的に参加し、後進の育成に努めている大西さん。それはかつての自分と同じように足を切断した人への思いがあるからです。
「私自身、鉄道弘済会や臼井さん、スタートラインなど、たくさんの出会いに恵まれて幸運だったので、少しでも多くの可能性を届けたいと思っています。必ずしも競技大会を目指さなくてもいいんです。スポーツ用義足を使えるようになると日常生活も楽になりますし、義足の仲間ができることで色々知ることができて、温泉に行けるようになったりね、健常のコミュニティにも参加できるようになって、行動範囲も広がりますから」(大西さん)
義足体験会を終えて、一日を振り返る執行さん。
「とりあえず自分は杖を外せることが第一歩。今回こうして杖なしで走れたので、続けていけば、それも夢じゃないのかなと自信がつきました。今日はありがとうございました」と充実した表情で運動場を後にしました。

遠く感じていたことが、自分の世界の一部になる、人生でそんな経験はこれからも、何度だってできるはずです。スポーツ用義足で走ってみたいかたは、ぜひ一度挑戦してみてください。
義足体験会の後日に開催される「発掘プログラム」の競技体験会では、義足体験会で自分用に調整された義足をつけて、希望するスポーツを体験することもできるそうです。勇気を出して、新たな世界へ一歩踏み出してみましょう。
義足体験会の概要や今後の予定については、発掘プログラムのホームページをご確認ください。
東京都パラスポーツ次世代選手発掘プログラム
https://www.para-athlete.tokyo/