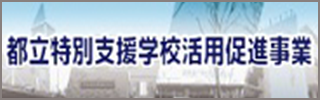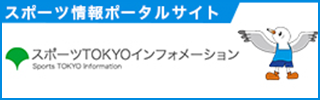水泳は結果が見えるのが面白い
自己ベストを出したときがいちばん嬉しい
今までの自分を超えたことになるからです
明るく朗らかな笑顔が印象的な星泰雅(ほし たいが)選手は、初出場の第23回夏季デフリンピック競技⼤会サムスン2017(以下、サムスン2017大会)で二つの銀メダルを獲得、続く第24回夏季デフリンピック競技大会ブラジル2022(以下、ブラジル2022大会)ではデフ水泳日本代表キャプテンも務めたチームのまさに大黒柱。現在は更に水泳に専念できる環境を求め、先輩選手のいる関西に拠点を移し練習を重ねています。10月末の少し肌寒く感じる頃、トレーニング中の星選手を訪問。東京2025デフリンピックが間近となった今の思い、これまでの道のりを伺いました。
2025年2月17日公開

子供の頃の習い事から、本格的に競技へ
5、6歳の頃に水泳を始めました。僕が喘息を持っていたので、母が健康のために水泳教室を勧めてくれたのがきっかけです。その頃は競技ではなく、楽しく運動しようという感じで、本格的に競技に取り組むことにしたのは高校に上がってからです。中学の地区大会で入賞したとき自分より速い選手がいて、自分は今後どれくらい速くなれるのだろうというちょっとした興味から、地元宮城の強豪校、東北高校※に入りました。高校水泳部での3年間で、結果的に100mの自己ベストを約30秒縮めることができました。最初は全く泳げず、練習についていくので精一杯、本当にしんどかったのですが、それでも心から水泳をやめたいと思ったことはありませんでした。
※学校法人南光学園東北高等学校(東北高校)—羽生結弦選手やダルビッシュ有選手などトップアスリートを数多く輩出するスポーツの強豪校。
聴者と肩を並べて練習する
僕は生まれてからずっと一般の学校に通っていたので、その雰囲気には慣れていましたし、聴者と一緒に泳ぐことにもあまり抵抗はなかったです。初めて補聴器をつけたのは小学校に上がる前で、補聴器をつけると大体は聞こえています。普段のコミュニケーションに問題はないのですが、プールに入るときは補聴器を外すので、比較的聴力の良いほうへ耳を傾け情報を取りますが、声の大きさによっては聞き取れないこともあります。

日本代表までの道のり
デフリンピックの存在を知ったのは小学6年生のときでした。その頃は競技として取り組んでいなかったので自分が出たいという気持ちはなく、高校の水泳部顧問の先生から「聞こえないということは、ろう者の大会にも出られるんじゃないか」という言葉を頂き、「デフリンピック」というワードが見つかりました。すぐに一般社団法人日本デフ水泳協会(以下、デフ水泳協会)に連絡して登録、その2年後にはサムスン2017大会に出場しました。デフリンピックの出場資格を得るためには、デフ水泳協会に所属し、強化選手に選考されたのち、指定の大会で選考基準となる「標準記録」を取ることが必要ですが、当時は道筋も何もわからず、デフリンピックが初めての国際大会でいきなりレベルの高い大会へ出ることへの不安もありました。実際は自分がイメージしていたものとは全く違い、現地の皆さんがすごく盛り上げていて「こんなにいい大会なんだ」と感じました。デフリンピックの場を経験でき、海外の選手とも交流すると「次も出てみたい、4年後に向けて頑張って練習したい」という気持ちになり、そこから次のブラジル2022大会まで練習を重ね、日本代表キャプテンとして出場させて頂くことにもなりました。
自身の強み、トップ選手に近づければメダルが見えてくる
自分の強みは、100m平泳ぎで後半からペースを上げていけることでしょうか。最初は遅れていてもジリジリと詰めて、盛り上がるタイミングでいけるところかな(笑)。また、トップ選手の泳ぎを動画などで見て、自分に何が足りないのか分析し、それを自分のものに吸収していくことも多いです。
ライバルという意味では、デフ選手だと2023年にアルゼンチンで開催された第6回世界デフ水泳選手権大会の平泳ぎ3位のクロアチア共和国の選手です。彼は自分の持ちタイムと近く、その人に近づければメダルが見えてくるので、自分としては彼がライバルなのかなと思います。

デフアスリートが直面する困難
苦労や克服ということでは、コミュニケーション方法がいちばん大変だったと思います。僕は分からないことは積極的に聞き、コーチやチームメイトも口を大きく動かすなど、はっきり教えて下さるので助かっています。ただ、中にはコミュニケーションが理由で、水泳をやめてしまう人が少なくないそうです。スポーツクラブでも耳が聞こえない人や聞こえにくい人を受け入れているところ、そうでないところがあり、練習場所を探すのがまず大変かなと思います。その悩みをどう打ち消したらいいのか僕も考えましたし、やはり筆談などで対応してもらえるとありがたいなと思っています。今僕は「デフ子供水泳教室」という小中学生対象のイベントをやっていますが、保護者からもコーチとのコミュニケーションをどう取っているかという質問がいちばん多いです。デフの人は目で情報を読み取るので、コーチの口の動きが分からない場合は、練習メニューを指差したり、ホワイトボードや紙に書いたり、そうした対応をしてくれる人がいるだけでも、すごく助かるのです。

チーム内でのコミュニケーション
実は僕は手話で話す方がスムーズなのですが、口話のできない選手がいて、チームとして伝えたいことがあるときは、手話と口話を使ってその選手とコーチの橋渡しをすることもあります。キャプテンとしては自分にできることは「盛り上げてみんなの士気を高めてチームをまとめることだ」と考え、試合の前などは、積極的に選手たちに話しかけて、緊張をほぐしたりしています。あんまり調子に乗って、逆に緊張を増やしたら申し訳ないなと思ったりはするのですけども(笑)。ほどほどに緊張を解くつもりでやっています。
一緒に練習してくれる先輩や仲間の存在
デフリンピックに出場経験のある現役の水泳選手は自分も含め男性3人、女性3人の日本代表選手がいます。
そのうちの2人、先輩の金持義和(かなじよしかず)さん、齋藤京香(さいとうきょうか)さんとは仲が良く、3人で練習に励んでいます。毎日大体6000m以上泳いでいますね。金持さんと一緒に陸上トレーニングでの補強練習もしていますが、後半のタイムを上げていけるようになったのはその成果だと思います。また、一緒に練習している聴者のトップ選手がいるのですが、泳ぎや陸上トレーニングでの体の使い方などをアドバイスいただいて、頑張って練習しています。

パラ/デフスポーツを始めてみたい方へ
障害によってできることできないことはあると思いますが、幅広くいろんなスポーツをやってみる気持ちが大事だと思います。始めるときに不安を感じる方もいると思いますが、そういう考えは一切なくして、とりあえずやってみようかな、楽しくやろうかな〜と、気軽に臨んでもらった方が逆にやりやすいですよね。水泳は老若男女、障害の有無を問わず誰でもできるスポーツですし、泳がないリハビリ目的の人もいますので、「泳げないから」なんて気にしなくていい、水泳って楽しいですよということは、みんなに伝えられたらいいなと思います。
今までの自分を超えていく楽しさ
子供の頃から、水泳は結果がはっきり見えるのが面白いと感じていました。自己ベストを出したときの気分は最高で、それは今までの自分を超えたということになるからです。まさに「いちばんの敵は自分」です。この数年ずっと自己ベストを連発している状態なのですが、それがあるからこそ、こうして今も楽しく水泳ができているのかなと思います。

東京2025デフリンピックに向けての思い
自分にとってはメダルを獲得したいという気持ちと、やはりお世話になっている人、応援してくれる家族、友達といったみんなに恩返しできたらと思っています。練習はきついですが、それを乗り越えようという気持ちで日々頑張っています。